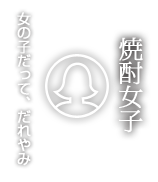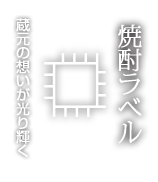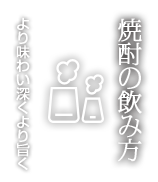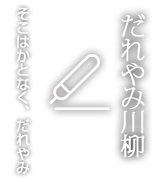小玉醸造の歴史
「一途に醸す」
日南市飫肥の城下町に、1818(文政元)年に創業したと伝えられる小玉醸造。平成に入ってしばらく休蔵していたのですが、2001(平成13)年に金丸一夫氏が継承し、息子で杜氏の潤平氏とともに焼酎造りを再開しました。一夫氏はもともと宮崎市内で代々続く酒造蔵を経営しており、潤平氏は東京農業大学醸造学科を卒業後、清酒蔵で修業を積み、蒸留酒が造りたいと帰郷。県内の焼酎蔵でさらに技術を磨いていました。その頃から杜氏として高く評価されていたといいます。
「潤平に思い切り造らせたいと思い、蔵探しをしていたところ小玉醸造と出会い、一家で飫肥に移り住んだんです」と一夫氏。一年あまり蔵の改修に費やし、2002(平成14)年11月から醸造をスタート。「造り方や蔵のあり方など、お互いの考えをじっくりと話し合った」という二人は、無我夢中で一番酒を造り上げました。
「自分たちの想いがすべて詰まった一番酒は、本当に素晴らしい出来でした」と一夫氏が話すよう、発売された『杜氏潤平』は瞬く間に全国で脚光を浴びます。2年目からはプレッシャーだったと振り返りますが、「原料の品質に左右される中で、期待に応える造りをしなければならないのが、小さい蔵の手造りの大変さでもあり、よさでもあります」と一夫氏。潤平氏が一途に醸す焼酎を、心待ちにしている人が年々増えていると話します。
小玉醸造の焼酎
スピリットが詰まったスピリッツ
一夫氏と話をする中で、印象に残った言葉があります。「スピリット(spirit)は精神や魂という意味ですが、蒸留酒のことをスピリッツ(spiritの複数形)と言いますよね。造り手のスピリットが詰まっているお酒だから、そう呼ばれているのではと考えます」。
「量」より「質」を追い求める小さな蔵の焼酎造りは、芋の選別から手麹、櫂入れなど五感をフルに使う伝統的な技術と、現代の機械が上手に融合されています。そこに造り手のスピリットが加わることで、「繊細さ」「調和」「余韻」のバランスがとれた焼酎が醸し出されています。
新品種「コガネマサリ」を初めて使用
「杜氏潤平」の原料となっているのが宮崎紅(べに)という芋。糖度が高く、主に食用の芋として栽培されているものを使用しています。
夏に楽しんでもらう焼酎として期間限定で販売している「夏の潤平」は、新品種「コガネマサリ」を使用。県が「黄金千貫」に次ぐ品種をと試験栽培していた「コガネマサリ」を初めて使用して造った焼酎です。宮崎県食品開発センターが開発した「平成宮崎酵母」を使い、優しく涼やかな味わいに仕上がっています。
小玉醸造の焼酎はアルコール度数が25度の銘柄がほとんど。「夏の潤平」は初めて20度に挑戦した銘柄です。ただ割水で薄めたというのではなく、原料や造りをこだわり抜いた一本です。ラベルにもちょっとした遊び心が。今夏ぜひチェックしてみてください。
造りへのこだわり
伝統の技・手麹(てこうじ)
多くの蔵元が製麹機で麹を造っている中、小玉醸造は手麹にこだわります。甑(こしき)で蒸された米や麦を冷却し次々と麻布に受け、一次室(むろ)へ運びます。
一次室で麹菌を種付けし、温度を見ながら床もみや切り返しをして繁殖を促していきます。一日経ったら二次室へ移し、箱に小分けしてしっかりと麹菌が付くようにして一晩おきます。そうして出来上がった麹は、一次甕で酵母と水と合わせて発酵させ一次もろみ(酒母)となります。
手麹を実際に見せてもらいましたが、とにかく体力勝負!見ているだけで肩に力が入ってしまいました。蔵人全員があうんの呼吸で作業を進め、素早く一次室へ。蔵は緊張感に包まれ、言葉を発することもためらってしまう雰囲気。誰もが一心不乱に自分の役割を果たしていました。その姿を見て、一夫氏が言われていた「みんなが気持ちを合わせる」ことの大切さが分かったような気がしました。
蔵人紹介
潤平氏コメント
焼酎は一年に一回、その年に収穫された原料を使って造る「一期一会」のもの。いかに気持ち良く発酵してもらえるかを考えながら、真摯に向き合って造っています。「焼酎」が「笑酎」と呼ばれるようになるくらい、多くの人に楽しんで飲んでもらえたらと思っています。
【写真】蔵元 金丸一夫氏(中央)、杜氏 金丸潤平氏(左から3人目)と蔵人たち
会社概要
| 会社名 | 小玉醸造合同会社 |
|---|---|
| 住所 | 宮崎県日南市飫肥8-1-8 |
| 電話 | 0987-25-9229 |
| FAX | 0987-25-1424 |
| 蔵見学 | 不可 |